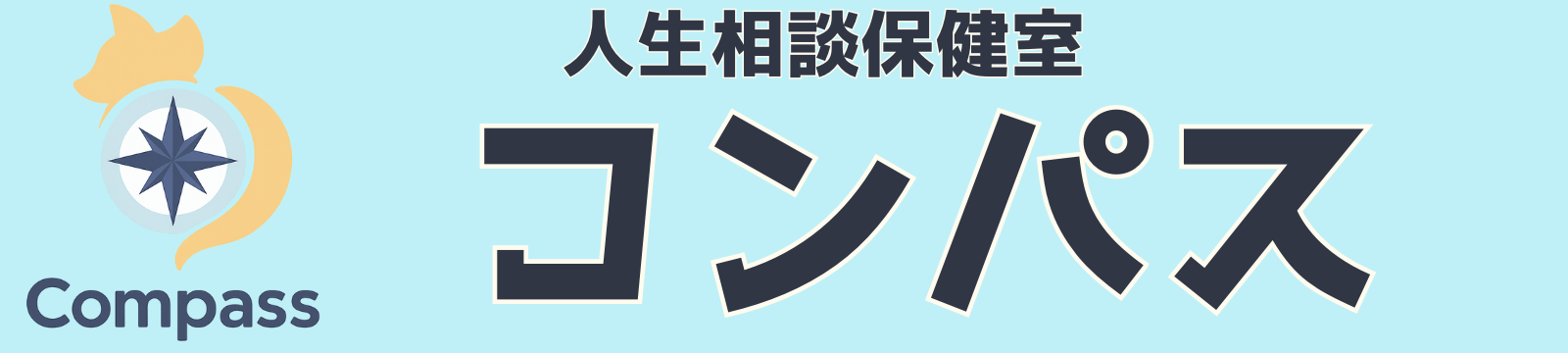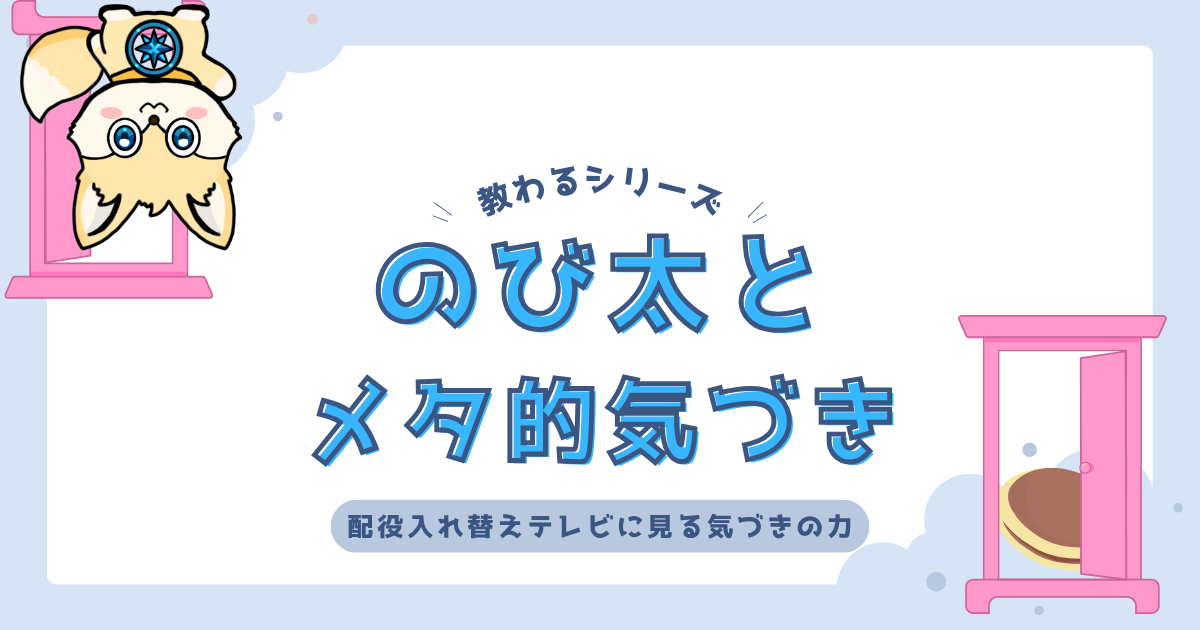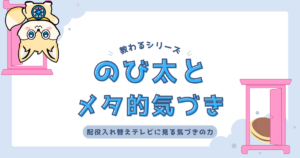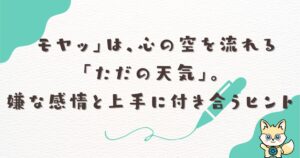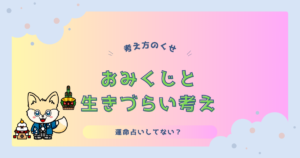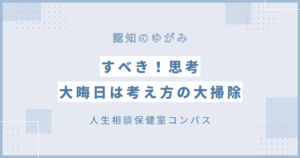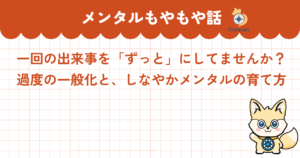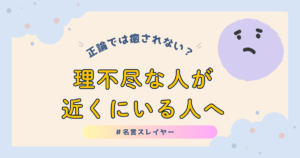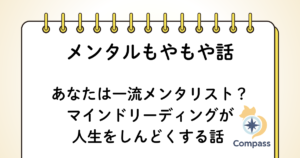🪞ドラえもんの「配役いれかえビデオ」に見る、気づきの力
ドラえもんのエピソードの一つに、転校生・多目くんが登場する話がある。彼は、のび太よりもさらに不器用で、何をしてもうまくいかない少年として描かれている。運動も勉強も苦手で、テストは0点。その姿に、のび太はどこか安心したような表情を見せる。「ぼくよりダメな子がいる」──そんな小さな安堵。
人は不安を感じると、無意識のうちに「自分より下」を探して安心しようとする。それは誰にでもある自然な心の働きだが、同時に、他者を比較の材料にしてしまう危うさも含んでいる。
のび太は悪意があったわけではない。むしろ“助けてあげよう”という気持ちすらあったのかもしれない。
一緒に宿題をしては、「そんなこともわからないの?」
一緒にかけっこをしては「また僕の勝ち!」
いつしかその関わりは、自分の優位性を確かめる行動に変わっていく。この微妙なズレこそ、人間らしい複雑さを映している。
そんな中、ドラえもんが取り出したのが“配役いれかえビデオ”。登場人物の役割と外見・声を入れ替えて再生する道具だ。ドラえもんは、のび太と多目くんのこれまでのやり取りを録画していて、再生するときにその配役を入れ替えてみせる。
のび太はスネ夫の姿と声になり、多目くんはのび太の姿と声になって、今までの2人の場面が映し出される。画面の中で、スネ夫(=のび太)がのび太(=多目くん)を見下ろし、軽い調子で言葉を投げかける。
その映像を見つめるのび太の表情が、一瞬で固まる。いつもスネ夫に言われて傷ついていた、あの言葉や態度を、自分が同じようにしていたという事実。それがまっすぐ心に突き刺さる。
これは「もし自分がスネ夫だったら」という想像ではない。自分が加えた言葉と仕草を、他人の立場を通して“客観的に再体験する”ことだった。のび太の胸の奥に生まれたのは、反省ではなく、痛みを伴う理解。その瞬間、彼は初めて“自分の行動が誰かにどう映っていたか”を知る。ドラえもんは何も言わない。ただ、のび太の中に芽生えた気づきを見守っているように描かれている。
メタ認知という鏡
このシーンが象徴しているのは、メタ認知であるといえる。メタ認知とは、自分の考えや心や行動を少し離れた位置から見つめる力。感情の中にいるとき、人は自分の態度の影響に気づけない。だが、視点を外に移した瞬間、自分がどんなふうに他者に映っていたかが見えてくる。
のび太が体験したのは、「他人になる」ことではなく、自分の行動を自分の外から見ることであり、さらには他者の気持ちを知るために配役を入れ替えるというメタ認知的技術(道具の力ではあるが)。まさにメタ認知と言ってよいものだった。
🌐 参考:ドラえもん公式より
ドラえもんたちのメッセージを毎日投稿中!
今日は「ぼくよりダメなやつがきた」からこのひとコマ✨️
pic.twitter.com/pINzHNDHmd— 【ドラえもん公式】ドラえもんチャンネル (@doraemonChannel)
September 1, 2025
日常で使える「入れかえ」の想像力
この話が伝えているのは、“誰かを見下す心”を責めることではない。その心を見つめ直す勇気のほうである。人は誰でも、知らないうちに誰かを踏み台にして安心しようとする。それに気づいた瞬間にこそ、優しさは始まる。
私たちは日常の中で、“配役いれかえビデオ”のような道具を使うことはできない。けれど、想像の力を使えば、心の中に同じ装置を持つことはできる。たとえば誰かに苛立ったとき、「もし自分があの人と同じ場面に遭遇したら? 同じことを誰かに言われたら?」と静かに問う。ほんの数秒でも、視点を入れ替えてみる。そのわずかな想像が、他者理解の最初の一歩になる。
メタ認知とは、難しいトレーニングではない。「わからないけれど、わかろうとしてみる」。その姿勢が、人の心をやわらかくする。
ドラえもんの“配役いれかえビデオ”は、未来の便利道具というより、心の成長を映す鏡として描かれている。のび太が感じた胸の痛みは、後悔ではなく理解の証。痛みを通して、自分を少し客観的に見られるようになったその瞬間、彼は一歩だけ、やさしくなった。
メタ認知トレーニングの位置づけ
一般的には社会人として成長するツールとしてのメタ認知トレーニング、専門的には、うつ病の方や、考え方のくせに対するメタ認知トレーニングなど複数の種類がある。共通して言えることは、メタ認知とは、他人を理解するための力であり、同時に、自分を赦すための力でもあるという点ではないかと思う。
カウンセラー ゴウ(保健師)
※本コラムは心理教育を目的とした内容です。
診断や治療を行うものではありません。